– 環境DNA分析手法 –

環境中のDNAを分析し、複数の生物種を同時に特定する手法です。この方法では、特定の分類学的グループ(例えば、魚、水生昆虫、哺乳類など)のDNAを増幅し、次世代シーケンサー(NGS)を用いて塩基配列を解読します。これにより対象のグループのうち、どの種が周辺に生息しているかを把握します。これにより、特定の地域に生息する生物の全体像を把握し、生態系の変化や生物多様性の評価に役立てることができます。
特定の生物種のDNAのみをターゲットにして検出・定量する方法です。この手法では、対象とする生物種のDNA配列に適したプライマーを用いて、サンプル中に含まれているその生物のDNAの量を特定します。網羅的分析と比較してより高感度かつ分析時間が短いため、希少種の生息確認や外来種の早期発見など、特定の生物を重点的に調査する場合に非常に有効な手法です。

– 環境DNAが注目される理由 –
効率的な調査手法
従来の生物調査では、対象とする生物を実際に捕獲したり、現場で観察したりする必要がありました。しかし、環境DNA分析を活用することで、水や空気、土壌を採取し、そこに含まれるDNAを分析するだけで生息する生物の種類を特定できます。これにより、調査にかかる時間やコストを大幅に削減でき、より広範囲かつ迅速な生態系の調査が可能になります。
環境への負荷が少ない
従来の調査方法では、対象生物の捕獲や標本の採取が必要となるため、調査自体が生態系に影響を与える可能性がありました。一方で、環境DNA分析は非侵襲的な手法であり、生物を直接傷つけることなく、生態系の情報を取得することができます。そのため、特に希少種や、生態系への影響を避ける必要がある場所の調査において有効な手法とされています。
幅広い応用範囲
環境DNA分析は、さまざまな分野で活用されています。生態調査では、野生生物の分布や生態系の変化を把握する手段として利用されています。また、希少種保全の現場にも活用され、従来の調査では発見が難しい希少種を検出することが可能になりました。さらに、外来種の早期発見にも役立ち、侵入した外来種を迅速に特定することで生態系への影響を未然に防ぐことができます。
– 環境DNAの可能性 –
希少種の発見・保護!
環境DNA技術は、これまでの調査では発見が困難だった希少生物の保護に大きく貢献しています。例えば、日本の絶滅危惧種であるニホンウナギの生息域調査に環境DNA分析が活用されており、より正確かつ効率的な保護活動が可能になっています。この技術により、生息が不明確だった生物種の存在を確認できるため、保護計画の立案にも役立ちます。
外来種の早期発見!
外来種は、生態系に深刻な影響を与えることがあり、その早期発見と対策が重要です。高感度な環境DNA分析を活用することで、目視では発見が難しい侵入初期の外来種の存在を迅速に特定し、適切な管理措置を講じることが可能になります。これにより、外来種の拡散を未然に防ぎ、生態系への影響を最小限に抑えることにつながります。
産業分野への応用!
環境DNA技術は、生態系の保護だけでなく、産業分野にも応用されています。例えば、水産業では、漁業資源の持続的な管理に活用され、乱獲を防ぐための重要なツールとなっています。また、農業では、土壌中の微生物DNAを分析することで、作物の生育環境を改善し、収穫量の向上に貢献することができます。これらの応用により、環境DNA技術は持続可能な社会の実現に向けた重要な技術として注目されています。
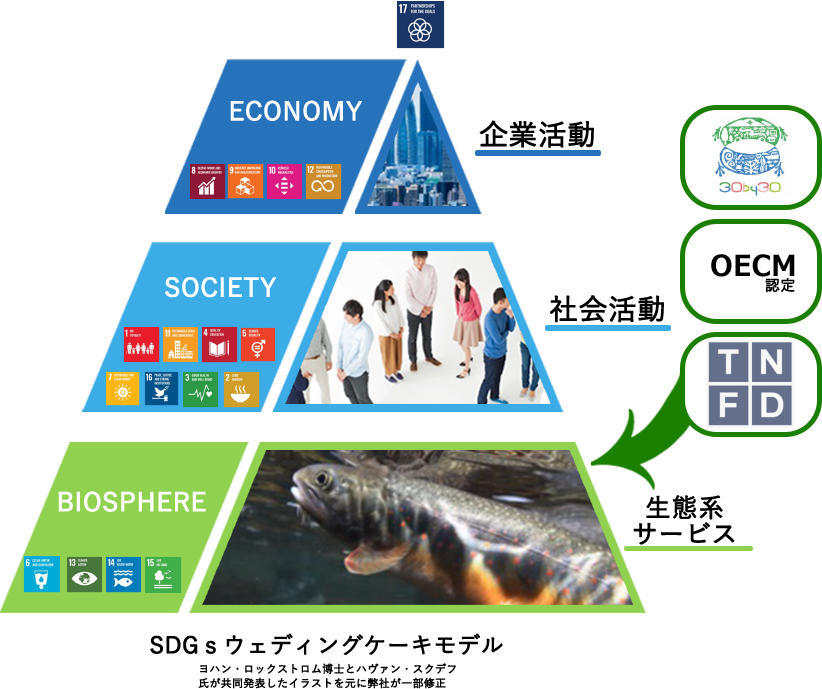
– 環境DNAを使った調査の流れ –
※河川における魚類調査の場合
① 調査計画の立案(事前準備)
調査の目的についてヒアリング。分析方法や対象魚種を選定。採水時期や採水地点を決定。
② 採水(現地調査)
計画した採水地点で、採水キットを使用し1Lの河川水を採取。DNAの分解抑制剤(BAC;塩化ベンザルコニウム)を添加する。
③ サンプルの発送
採水した河川水を冷蔵にて当社環境DNA分析センターへ発送。
④ DNAの抽出と精製
ろ過装置を使用し、水中の環境DNAをフィルターに捕集。DNA抽出キットを使用し、フィルターからDNAを抽出し、サンプルを保存。
⑤ DNAの増幅(PCR)
DNAを増幅するためのPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)を実施。複数種の生物を対象とする場合は「網羅的分析(メタバーコーディング)」を実施。特定の生物種をターゲットにする場合は「種特異的分析(qPCR)」を実施。
⑥ 網羅的分析と種特異的分析
網羅的分析の場合
増幅したDNAの塩基配列を解析(次世代シーケンサーを使用)。データベースと照合し、魚類相を特定。調査地点ごとの魚類リストを作成。
種特異的分析の場合
プローブ法によりPCR中に発生した蛍光から対象種のDNAの量を定量。
⑦ 結果の解釈と報告
魚類の分布や変化を調査レポートとして報告。希少種の生息確認、外来種の侵入状況などを分析。
⑧ 調査完了
環境DNA分析による調査は、生き物を直接捕獲せずに生態系の現状を把握できるため、従来の生態調査よりも効率的かつ負担の少ない手法です。また、広範囲の調査が可能であり、短期間で多地点のデータを取得できることから、環境保全や水産資源管理、外来種対策など、さまざまな分野での活用が期待されます。
環境DNAによる調査をご検討されている方へ